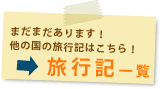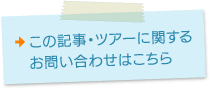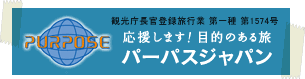羽田を夜00:05に発ち
ヨーロッパのハブ空港、ドバイで乗り継ぎし、プラハには予定より30分も早い12:30に到着した。日本より7時間遅れているので日本時間では19:30着、すなわち19時間25分かかったことになる。これほど長い距離を1回の旅行で飛ぶのは初めての経験であった。
プラハ空港は日本の空港のようにゴミ一つなく、清潔なイメージを与えて快適である。心配だった荷物も無事到着し、いよいよチェコの旅の始まりだ。空港に迎えに来てくれた車の運転手とも予定通り会うことができ、プラハの街に向かった。
ホテルにチェックインし、直ぐに眠り込んでしまったが、夕方5時になっても街は明るく、人通りがある。夕食を兼ねて街に出てみた。日差しも強く、通りには外国人旅行者が列を成して歩いている。団体旅行が好きなのは日本人ばかりかと思ったが、ドイツ人、韓国人、フランス人、イタリア人のグループや修学旅行らしき学生グループなど、道路に溢れるばかりだ。チェコの観光産業は2020年にはGDPの3%程度だったというが、コロナが明けた2024年では実感としてこの倍の拡大があるのではないかと思えるほど観光客で賑わっていた。
ヨーロッパのレストランはお店の中で食べるより外のパラソルを張ったテーブル席を好むようだ。
ビールやワインを明るいうちから飲んで歓談している。これがまた、客を引き込む要因になっているようだ。私たちもイタリア系のレストランに入ってみた。パスタ、リゾット、アヒージョ、ピザなんでもあり楽しい雰囲気だ。自然に隣のテーブルの人たちと会話になる。サウジアラビアからきた家族は陽気で自分の孫の話をしたかと思えば、携帯で孫とTV通話をし始め、孫を見せてくれた。画面の向こうでフィリピン人のメイドがあやしており、私も孫に話かけたりで、陽気な家族に出会って楽しかった。
そろそろ夜で疲れも出始めたので、ホテルに帰った。ついた瞬間、ばったり死んだように眠ってしまった。
ふっと起き上がった妻がなんかおかしいと言う。今9時だけど、次の日の朝の9時かと言う。確かに外は明るく、次の朝まで寝過ごしてしまったのかと思い、携帯電話に目をやったら21:23とあり、安心した。翌日の朝7時にはモラヴィア草原に出かけるため車がホテルに迎えに来ることになっていたので、どっきりした。
プラハはこの季節、日没時間が遅いそうであるが、まさか、9時過ぎまで明るいとは知らなかった。因みにチェコで日照時間が最も長いのは7月で、一日20時間近くあるようだ。
翌日、予定通り運転手が迎えに来た。
名前はジョンさん。時々、小雨がぱらつく天気であったが、モラビア草原の雄大さには心を奪われる。現地の人はなぜ、日本人がこうした草原が好きなのか分からないようだ。日本は山の多い国で、かなたまで麦畑が広がる平原はないため憧れを持つのかもしれない。
どこまでも続く草原、トラクターが入る轍が黒い線となってアクセントをつけている。車でプラハから2時間半の距離でこうした大草原があるのは羨ましい限りである。道路事情も良く、スピード制限は時速130キロであるが、ドイツのアウトバーンのような道が草原を貫いている。
プラハに次ぐ第2の都市ブルノにあるトゥーゲントハット邸という三大建築家の一人ルードビッヒ・ミース・ファンデルローエという建築家が設計したという邸宅を見学した。美しい書斎、リビング、寝室と庭など一見の価値はある。また、その邸宅街に立ち並ぶ家々を見るのも楽しい散歩となった。
時間があったので、ナポレオンも泊まったというSlavkov(スラフコフ)宮殿を案内された。石畳が続く庭には赤い実をつけた大きなプラタナスが長い時を見守ってきたかのように立っていた。時計台の鐘の音が300年も前と同じ音を響かせているかと思うと、暫し、足を止めてしまう。
石畳の模様を楽しみながら、Starobrnoの大きな看板が出ているビール工場にきた。Starobrnoはチェコで有名なビール銘柄で、ビール工場に隣接した大きなレストランも経営している。お昼はこのレストランで、代表的なチェコ料理である牛のGulash(ビーフシチューのようなもの)と白くて柔らかいパンのようなもの(ダンプリンと呼ぶ)を食べてみた。ビーフシチューと同じ味がした。
帰路は、ホテルまでは若干、交通渋滞はあったが、5時には帰還した。
翌日は観光客がもっとも集まる旧市街広場に出かけることにした。
ホテルから歩いて10分程である。観光と食の中心というイメージで、世界各国からありとあらゆる人々が集まっている。まさに人種のるつぼである。ティーン教会、聖ミクラーシュ教会、13世紀から15世紀に建築されたと思われるゴシック作りの大聖堂は圧巻であり、街全体が世界遺産に指定されている理由がよくわかる。
天文時計という15世紀ごろに作られた時計台は毎正時になるとカラクリ人形が動き出す仕掛けの時計台で人気があり、毎正時少し前になると、群衆で埋め尽くされ、オーバーツーリズムそのものである。しかし、これほど多くの人が飲んだり食べたりしているのにゴミはほとんど落ちていない上、トイレはどこに入っても清潔で使い易い。おそらくチェコ人の国民性はキレイ好きで、外国の人を接待しようと言う気持ちに溢れているのかもしれない。
私たちがプラハでしたかったことの一つにクラシック音楽の鑑賞があった。
大きなオーケストラは日本と同じで何週間も前に予約してなければ難しい。しかし、弦楽四重奏であれば、街中のインフォメーション・センターでチケットを購入できる。一人5~6千円である。
私たちは毎週土曜日の夕方5時に開演するコンサートを幸いにも聴くことができた。会場は昔の古い教会(St.Martin in the wall)で行われた。曲目は、有名なスメタナの「ボルダウ川」から始まった。素晴らしいストリングスの流れは正にボルダウ川の哀愁を誘うものであった。
ビバルディの四季、ドボルザーク(チェコ人)の新世界、モーツアルトのDivertimento in F、と続いたが、第1バイオリンの女性奏者の演奏の素晴らしさには圧倒され、まるでオーケストラを聴いているようで、4人のカルテットがこれだけの音を出せるとは驚くばかりだった。
毎日、プラハを歩くのはとても楽しい。
ボルダウ川の河畔へと歩き、20分ほどでカレル橋まできた。なんと清々しいところなのだろう。人の肖像画を描く絵描きやクラフト製品の土産を売っている人が店を並べている。
カレル橋を渡るとプラハ城の城壁に囲まれた城内へと入っていく。長い丘を30分程歩くと丘の上に出て、プラハの街を一望できる。見晴台の横にスターバックスがあり、こんなところにもスタバかと思っていたら、ガイドブックに世界一見晴らしの良いところにあるスタバとのことで、店からの眺めはコーヒーを3杯は飲める時間を作ってくれだろう。
城内にはゴシックの聖ヴィート大聖堂があり、全ての王様は神様ととともに暮らしていたようだ。
興味は尽きないが、そろそろお土産を買わなければいけないと思い、日本のお寺の参道に並ぶ土産屋のようなところに次々と入り、いくつか買った。買ったものはマグカップ、ビールグラス、クリスマスツリー用アクセサリー、コースター、スケッチ画、風景皿、グミ、クッキーなどで、しばらくしたら、机の隅のスケッチ画がチェコを懐かしく思い出させてくれるだろう。
![旅行記[旅のクチコミ情報]](/assets/css/gone/head.gif)