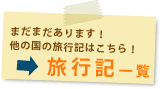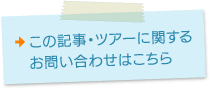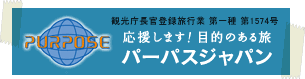【 ウズベキスタンの足の爪をなでる 】
人もすなるシルクロード行(こう)というものを、我もしてみんとて、頼もしい山女、友人Sを誘って、勇躍、ウズベキスタン、タシケント空港に降り立ちぬ。と書くと、筆者としての私は、やはり、ほら男爵のそしりを免(まぬか)れないだろう。だが、事実、10月初旬に、我々はパーパスジャパンの二人ツアー催行の英断によって、ウズベキスタンを旅した。
8日間、実質7日の期間での見聞は、ウズベキスタン共和国という象の、足の爪のほんの一部を撫でたにすぎないが、この旅によって得たものは多大である。
成田から9時間を飛行して着いた空港で、待っていたのは、美しい灰色の瞳をしたロシア人女性ガイドのTさんと、男性運転手Uさんである。
このTさんの案内によって我々は、タシケントを皮切りに、ヒヴァ、ブハラ、シャフリサーブス、サマルカンドを経巡(へめぐ)る旅に出発した。
4つの町はタシケントを除いていずれも世界遺産に登録された地区を持ち、我々のツアーは、いわば遺産巡り、という側面を持っている。
1. ヒヴァ
最初の地ヒヴァは、南に国境を接するトルクメニスタンに、円盤型UFO状に出っ張った、その先端にある。タシケントから空路1時間40分、西へ西へと飛んでウルゲンチ空港へ、そこからさらに車で40分、という行程である。
ウズベキスタンは、領域の大半が砂と小石の、いわゆる礫(れき)砂漠で、その所々に人々は、オアシスを造って町とした。ヒヴァも、その一つである。古くから水源はアム川(アムダリア)に依っている。現在は川に平行にした、アラル海からの運河もあり、それらの水で街は潤(うるお)され、農地は灌漑されている。
だが、ヒヴァの世界遺産イチャン=カラ(二重都城の内側の都城)の外周は、乾燥した地面が続いていた。所々に背の低い灌木(かんぼく)と草が生えているだけである。草の葉はすべてトゲになっている。観葉植物のアスパラガスは、その枝を葉のようなものに変化させたが、その内の一種に、この草はそっくりだった。Tさんはその名を、ラクダ草だと教えた。ラクダは好んで食べるが、トゲを嫌うのか、羊は仕方なく餌にするという。
内城イチャン=カラの城壁は、この乾燥した土と、それを素材としたレンガで建造されている。建造年代は17世紀か、ヒヴァが名実ともにヒヴァ=ハン国の都となった頃、とされている。ガイドブック『地球の歩き方 中央アジア』に、高さ8~10m、厚さ6m、周回2,250kmとある、巨大なこの城壁の写真を、さる雑誌で見たことが、今回の旅を決意する直接の契機となった。それゆえ、城壁を眼前にした時の感慨は、文字通り、無量であった。
ツアー応募を決めた前後に、ウクライナの騒動、民間機の墜落、さらに「イスラム国」の「樹立」をめぐる騒擾(そうじょう)、などが起こった。友人Sは家族の説得に追われた。しかし個人的に大きかったのは、9月に入ってからの、体調不良、眼の痛み、歯の欠落と歯痛である。そしてそれを追い討ったのが『歩き方』の記述にいう、役人の権威主義、治安、衛生上、等の不安である。眼と歯の治療に追われている身で、飲めない水を使っての、洗眼、歯磨きが、どのような影響を及ぼすか、第一、旅行するだけの体力は有るのか――。
決行か、断念か。しかし、友人Sを誘ったのは自分であり、ツアーは二人としての「催行確定」を見ている。出発目前の気持は、義務感だけだった。
そして――だが、と言うべきか、眼の前にイチャン=カラは聳(そび)え立っている。「今、ここに来た!」のだ。
都城内に建つさまざまの建築物のなかで、心が留まったのが、ジュマ=モスクである。10世紀に建てられたというそれは、木材の目立つ建物である。中央の広間を囲む回廊には、木の天井を支える木柱群が立ち並んでいる。当時の外国から贈られた柱も何本かあった。一本一本の各々には、異る細かい浮き彫りが施(ほどこ)されている。そして柱は、いずれも胴が膨(ふく)らんでいた。ヘレニズム文化との融合が、ここにも確かに存在していた。
次に、カズィ=カラーン=メドレセ(神学校)。ここには音楽と楽器の博物館がある。今度の旅の目的の一つで、Tさんに案内をリクエストしたものだった。ウードやシタールのような弦楽器が数種、打楽器タンブール、管楽器もあった。展示の楽器のなかで、ウズベキスタンに特有であるのが、長い大きなチャルメラだ、とTさんは教えた。40cm以上は有ろうかと思われるものである。博物館を出て表を歩いていた時、計らずも、城内のモスクを目差す、結婚式の行列が通りかかった。そのしんがりに付いた楽隊が、幸運にもその音を聴かせてくれた。この日、結婚式は3組は見かけた。
音楽についての幸運は、もう一つあった。
内城西門を入ってすぐ北にある、キョフナ=アルク(古い宮殿)のアクシェイフ=ハバと呼ばれる見張台でも、巡り合えたのだ。
見張台へ行くための石階段は、段差40cmはあった。垂直かと思われるほどの傾斜で、これを登るのは、9月中クリニックへ通う他は寝たきりに近い状態であった身には、三十数年前に松本城天守閣へ登って以来の「冒険」である。さすがに気軽げに登って行った山女Sの跡を、私は手すり(これがかなり揺れる)にしがみつきながら、一段ずつ「登攀(とうはん)」する(降りる時はさらに恐怖で(高所恐怖症)、あまりの無様さを見かねてか、下にいた人に途中から助け降ろされた)。
石階段を登り切ると、テラスがあった。そこで、縞(しま)に織った民族衣装の褞袍(どてら)様の着物を着た男性歌手が、ウズベキスタン歌謡を歌っていた。成田―タシケントの9時間の飛行中、繰り返し聞いた歌謡によく似た曲が、つい目の前で歌われている。写真を、とカメラ(使い捨て)を向けたが、スタッフが気づいて、レフレクターで遮(さえぎ)って邪魔をする。再三試みたがいずれも遮断され、さすがに、撮影については何かルールがあるのだろう、と気づく。邪魔をしたスタッフは笑顔で、ごめんね、撮らせてあげられなくて、という表情をした。
ウズベキスタンには操(あやつり)人形がある。
ワークショップがブハラにあり、人形の販売もしている、と『歩き方』は紹介しており、これも、旅の目的となっていた。
この操人形が、内城でも、土産物として売られていた。30cmくらいの大きさの男女ペアの人形を、壁掛け状の袋に入れて、18~20USドル程(ウズベキスタンの通貨は「スム」だが、観光地ではもっぱらUSドルが歓迎される)。もちろん欲しくてたまらなかったが、この日の朝、あまりの寒さに堪えかねて、ホテルで上着の購入に大枚(たいまい)をはたいていたので、買えない。私が逡巡(しゅんじゅん)していると見て取ってか、主(あるじ)のおじさんは、これらは自分が作ったもので、丈夫にできている、他の店の安物とは違う、と言いながら、自ら人形を遣(つか)って見せた。
男人形の名はアブドゥーラだ、と教えて、おじさんの取り上げた人形は、作り手にそっくりな顔をしていた。男女とも、頭は紙粘土、民族風の衣装をまとっており、袖の左右に、厚紙様のもので作った手が付いている。服の裾から手を入れて、この紙の手に小指と親指を差し込む。人形の頭には、竹の棒が差さっており、この竹の棒で、人形の頭を上下させ、左右に振らせる。すなわち人形は、片手で左右の手を遣い、片手で竹の棒を操ることで、動きと表情を持たせることができる。人形の首には、プラスチック製の円形の肩が付いており、人形の姿と動きをより自然に見せる。なんと、これは一人遣い人形、しかも兵庫県の神社に遺る能人形ではないか。ウズベキスタンの人形は期待以上だった。
おじさんとの、値段の交渉が始まった。「一つなら幾らなのか」「10ドル」「10ドルは出せない。7ドルではどうか」「おおマダーム(笑)、それは殺生な」「しかしお金はそれしかない」。ここでおじさんは、人形の出来の良さを、先程以上に口上(こうじょう)する。しかし、出せないものは出せない。でも欲しい。「8ドルでは?」と、ついにこちらが折れて、交渉は成立。「ラフマト(ありがとう)」を期待したが、おじさんは「サンキュー、マダーム。アリガト」と言って、にっこり笑った。
「ラフマト」は、ウズベキスタン行きに当たって、事前に覚えていった幾つかの言葉の一つである。「こんにちわ(アッサローム・アライクム)」は難物で、繰り返し練習したにもかかわらず、初対面の時にTさんとUさんに使って、けげんな顔をされた。上手に言えなかったか、と思ったのだったが、これは挨拶としてはかなり重い言葉のようで、あるモスクでは、坊さんと信徒がこの挨拶をおごそかに交わしていた。タシケントへ帰る列車の中で見たドラマでは、嫁が義父母に言っており、丁寧な仕種を伴っていた。
「ラフマト」は幾度か使ってみたが、相手の表情は変わらぬままで、以後止めにした。だがその「ラフマト」を、運転手のUさんがウズベク人の親切に対して使った。あるレストランに車を停めた時のことだ。そして相手の男性は表情を緩(ゆる)めて、何事か返事をしたのだった。Uさんはウズベキスタンが生活の地である。足の爪を撫でるのが勢一杯の、観光客ではない。観光地では(ホテルを含めて)、「ありがとう」は「サンキュー」なのだ。
一方で、日本人観光客である我々には、「アリガト」も度々使われた。「サヨナラ」も同様である。「ハイル(さようなら)」はついに一度も使わずにしまった。観光地内では、単語なら日本語も通じると知った我々は、もっぱらそれを使った。だが、シャフリサーブスの路上ですれ違った、小学校高学年位に見える少年に「コンニチワ」と声を掛けられた時は、さすがに驚いた。客引きの口からはよくその言葉が聞かれたが、彼は客引きではない。少年は実にうれしそうな表情で声を掛けてくれた。彼はどのようにして韓国人あるいは中国人と、日本人を見分けているのか。
私が目にした韓国人ツアー客は、何組もいた日本人のそれに比べ、一組だけだったが、我々の泊ったタシケントのホテルでの食事の時、一緒になったのは韓国人と中国人である。家族づれが半分、あとはビジネスマン風の人々だった。ホテルの各国時間時計に選ばれていたのはソウルであり、タシケントのバザールでは、朝鮮料理の材料がふんだんに売られていた。後になって、かつてウズベキスタンに強制移住もしくは抑留された朝鮮族の子孫が、今も同国に住んで、政財界で活躍していると知った。タシケントやサマルカンドには、サムスンのショップが何軒かあった。旅行中見かけた日本の電化製品は、先に触れたドラマを映していたシャープのTVだけだった。
旅行中に私は先の言葉の問題をはじめ、多くの事を学んだが、ヒヴァで学んだのは、大陸性気候と、そして多民族国家のありようである。大陸性気候、それも乾燥した地でのその過酷さ――。
ウズベキスタンの緯度はほぼ仙台に当たる、ということで、東京の10月初旬に着るにはやや温かい服装、厚い着地の麻と木綿の長袖シャツに麻の長袖上着、冬用のデニムを着用、他には厚手綿のワンピース、カーディガン、タートルネックのTシャツにトレーナーなどを用意、これらの着廻しで済むだろうと思っていたのだったが、初日のタシケントの夜に早くも、失敗だったと気付かされた。夜、ホテルでは暖房が施(ほどこ)されたのだ。
翌日、昼間は快適にすごし、午後の国内便でほぼ同緯度のヒヴァに着いても、何の支障も感じられなかった。しかし昨晩の経験から、Sがエア・コンの点検をすると、それは故障していた。「まぁお風呂があるからね、温まって早く寝よう」と彼女は言ったが、風呂の湯はついに出なかった。我々は着られるものはすべて着、予備の上蒲団(うわぶとん)を足して、ベッドカヴァーまで掛けて寝(やす)んだ。
ヒヴァでの二日目の朝、朝食にホテルの外へ出た時の体感は、東京の11月中~下旬くらい、レストランは暖房でぬくぬくと温められていた。Sは旅慣れていて、小型のリュックサックから魔法のように、気温に適した服を何着も、ジャケットまで取り出した。他方、麻と綿の服しかない身としては、それで外を歩くのは無謀である。思案の末、ついに裏付き上着の購入を決意したのだった。このホテルでの散財が、先に記した操人形を値切る、という初快挙につながった。
この日、ヒヴァでは日中も、この上着が不快に感じられるまでの、気温の上昇は無かった。Tさんの話では、日中半袖、夜ダウンの上着、という事もあるという。旅行中の昼夜の温度差は、さすがにそれほどではなかった。しかし乾燥した寒さは身に堪(こた)え、しかもその気温は日替りした。
この後、四日目のブハラ(ヒヴァの南東)と五日目のシャフリサーブス(ブハラの南東)では、8月のような暑さ、六日目のサマルカンド(シャフリサーブスの北、緯度はほぼブハラ)では、冬の寒さとなった。サマルカンドで見た結婚式の花嫁は、肩を露(あら)わにした白いドレス(流行らしい)を着ていた。東京なら今にも雪の舞いそうな灰色の空から、雪を防いでくれたのは、彼女の熱い幸福感であったかもしれない。
そして、民族の多様性。
かつて「日本は単一民族の国だ」と言って、世間と世界に驚かれた人がいたが、同様の発言は今も時折聞かれるので、そう思っている人はたくさんいるのかもしれない。多分は、単一の民族で成り立つのが国家だ、という考え方なのだろう。ウズベキスタン共和国の民族構成は『歩き方』の記載では、人口の80%弱のウズベク人と、5%弱のロシア人・タジク人、他にタタル人、カザフ人、他、そして国内の自治共和国カラカル=パクスタンに住むカラカルパク人など、となっている。右の民族は、ロシア人とタジク人を除いて、トルコ語系モンゴロイド、もしくはトルコ系、タジク人はいわゆる金髪碧眼の民族といわれるアーリア系である。
確かに、先の操人形作りの陽気なおじさんと、キョフナアルクの見張台にいた歌手とでは、顔立ちが明らかに違っていた。一人はトルコ系で、一人はモンゴル系の顔である。内城で店を出していたのはウズベク人と思われる人々が多かった。ヒヴァも含め、ホテルで働く若い男性に目立ったのは、Sの表現を借りると「皆、ダルビッシュ(投手)」の顔をした人々であった。
しかし正確に、彼らが何民族なのか、知ることはできなかった。区別できたのは金髪の女性たちである。だがそれも、ロシア人なのか、タジク人なのか、彼らと混血したウズベク人なのか。これほどに多様だと、豊饒(ほうじょう)な感じがする。しかし多様性は反面、混沌(こんとん)に繋がることがある。我々は毎日、その不幸な例をメディアで知らされている。民族の多様性は、国家というものが一体どういうものであるのか、ということを考えさせた。それは単に国境が行ったり来たりする、という事だけではなく、人間の本質が問われる問題である。
女性について見聞したことを記しておくと、髪の色眼の色にかかわらず、職に就(つ)いている女性たち――飛行機の客室乗務員にはじまって、空港でパスポート等のコントロールにたずさわっていた人々、ホテルの従業員、街のレストランや食堂のスタッフ、バザールの売り子――は、実に、すばらしく生き生きとしていた。
だが高等教育を受けても、ひとたび結婚すると事情が変わる、とTさんは言う。すぐに出産を望まれ、しかも一人産むと二人目三人目が続き、結局家庭から出られなくなってしまう、と。働いている女性の中には、既婚者と思われる人々もたくさんいたのも事実である。が、しかし、中年以上の専業主婦とおぼしき女性たちに、暗い眼をしている人がいるのも目にした。タシケントの公園などで、所在なげに屯(たむ)ろしていた若い男性たちも、そのような眼をしていた。
国家はガス田(でん)や石油を持ち、綿花畑を専有して豊かであるというが、失業率は、女性の就職の事情は、どうなのか、家庭の中で幸せに暮している女性も多いに違いないが、その辺の事情は、足の爪をなでただけではとうてい解らない。
さて、ヒヴァで多くの収穫を得て、再びウルゲンチ空港へ戻った我々は、そこから夜の便で空路1時間の、次の目的地、ヒヴァの東南に位置するブハラへ向った。
2. ブハラ
ブハラは、ウズベキスタンの歴史の中で、2回首都となった地である。一つはサーマーン朝、一つはブハラ=ハン国が、それぞれ首都とした。
7世紀初頭、預言者ムハンマドが啓示を受けて布教の始まったイスラーム(教)は、征服活動を伴って、ササン朝ペルシャの領域を呑み込み、7世紀の中期にウマイヤ朝、1世紀後にアッバース朝を建てて、イスラーム帝国となった。中央アジアのほとんどがこの支配に入って、イスラーム(教)を受容することになる。今、復興製造されているサマルカンドペーパーは、751年、大国唐と、前年に誕生したばかりのアッバース朝の、戦いの中からサマルカンドにもたらされたものだ(この戦いは結果的に、唐の西域支配を終わらせることになる)。
だが盛者必衰、アッバース朝に仕えた地方総督の自立が、9世紀後半、その域内に、イラン・アフガン系の王朝を開く。これがサーマーン朝であり、ブハラはその首都となる。アッバース朝は領域支配に苦しんで、やがて衰退の道をたどるが、サーマーン朝ブハラはアジア大陸の交叉点(こうさてん)として、イスラーム文化の中心となって、繁栄した。しかしこの王朝も、10世紀末に、トルコ系カラ=ハン朝に亡ぼされ、中央アジアはやがて、西方へ進出を始めたセルジュク族トルコの支配を受けることになる。先に訪れたウルゲンチ・ヒヴァ地方は11世紀末に独立して、トルコ系ホラズム朝を興すが、それも含めて13世紀初め、中央アジアは、チンギス=ハーンの征西に見舞われる。この征西によって、ブハラやサマルカンドは蹂躙(じゅうりん)され、破壊された、とされている。
西方に封じられたチンギス=ハーンの息子たちは、各々がその各地に国を建てた。中央アジアにはチャガタイ家のチャガタイ=ハン国、カザフ高原にはジョチ家キプチャク=ハン国、イラン高原には孫フレグのイル=ハン国が興こされて、やがてトルコ化、イスラーム化してゆく。そして14世紀後半、中央アジアは「破壊者」チンギス=ハーンに対比されて創造のシンボルとされる、チャガタイ=ハン国の軍人にしてチンギス=ハーンの裔(すえ)、ティムールの帝国となる。だが16世紀初頭には、これに替わって、ウズベク人がキプチャク=ハン国系のシャイバン朝を建て、ここからブハラ=ハン国が分立、ブハラはその首都となった。
ブハラ王国は、並立した王国ヒヴァ=ハン国ともども、19世紀後半、ロシア帝国の保護下に入るまで、近世、近代を生きた。このように、歴史の教科書から書き写すだけでめまいのする歴史を、ウズベキスタンは持っている。だが、世界の多くの国々は多かれ少なかれ、同様の歴史を持ち、一部では支配と独立の争いが続いている。
さて、ブハラは、二つの時代を首都として経験したため、各々の時代の優れた建造物がのこされている。
ブハラ=ハン国時代の建造物の代表は、歴代ハーンの住んだアルク(城)である。アルクの美しいレンガ積みの城壁は、姫路の白鷺城を思わせる。この城にも埋蔵金伝説があり、我々の興味を大いに引いた。
だが私が心を動かされたのは古い方の時代、サーマーン朝の滅亡後に、砂に没した建物である。20世紀初頭から発掘が始まり、今も続けられているが、その一つが、イスマイール=サーマーニ廟である。これは、イスラーム様式としては現存最古のもので、9世紀の終わりから10世紀中期にかけて、サーマーン朝の王イスマイールによって建築が始った。
ブルータイルを「見飽きた」Tさんは、この小さな廟の好もしさを、熱心に我々に語った。廟はレンガだけで建てられ、そのレンガの積み上げが、同時に見事な装飾となっている。実に個性的で、夏のようなブハラの熱い青空によく映えた。この廟には伝説があり、願い事を繰り返し唱えつつ右廻りに三回廻(まわ)ると、その願いは叶えられる、とTさんは教えて、私も叶った、と、ちょっといたずらそうに微笑した。日本の寺院にも似た言い伝えがある。墓石には賽銭が供えられ、今も巡礼者が訪れていることを知らせるが、彼らも何事かを願ったのだろうか。涼しい墓室から外に出るのは気が進まなかったが、立ちくらみしそうな日射しの中を、教え通り願い事を繰り返しながら巡回した。廟の死者に敬意を表しつつ。
我々は行かなかったが、チャシュマ=アイユブの泉の伝説も面白い。旧約聖書の予言者ヨブ(アイユブ)が杖で叩(たた)いた地面から、水が湧いて泉となった。この水湧伝説で名高いのは日本では空海だが、この分では空海同様、アイユブ杖立て掛けの石、なども存在するのではないか、などと密かに考えてみた。泉が湧いたのは12世紀、16世紀になっても建物は建て増しが続いたというが、ムスリムにとって、ヨブとはどのような存在なのだろう。
訪れたもう一つの発掘された建物は、これもレンガ造りのマゴキ=アッタリ=モスクである。今はカーペットの博物館になっている。
ここで見たのは、文化の重層だ。下に仏教の寺、その基礎の上にイスラームのモスクが建築された。ゾロアスター教の寺院も建っていた、とTさんに教えられ、階段脇に掘られた穴を覗き込む。仏教寺院の跡は真黒い土の層だった。大乗仏教がアレクサンドロス伝来の文化と出合ってガンダーラの仏像が生れた。そして今我々が見学しているのは偶像の替わりに別の文化を発展させたイスラームの古い寺院だ。ゾロアスター教は前7世紀ごろに、イラン東部で創始されたとされるが、Tさんの説明では、最近の研究はウズベキスタンを故地とするという。ゾロアスター教を具体的なものとして見たいという私の旅の目的は、ここで目をひらかれ、そして最終日のタシケント歴史博物館で果たされることになる。
ブハラ観光の前日の夜以降、眼と歯への不安から大量に持ち込んだ消毒液、除菌スプレー、除菌ティシューなどの、使用を止(や)めた。手は水道水で洗う。ペットボトルの水で濯(すす)いでいた歯ブラシも、同様にした。続けていた専用水での洗眼も中止することにした。ウズベキスタンの水事情がどのようであるのか、生活用水として使用されている水も、多くはアラル海から引かれた運河の水であろう。アラル海は枯渇しつつあるという。ホテルの水を東京と同様に使ってよいとは思わなかった。
しかし考えにのぼったのは環境問題ではなく、とりあえず衛生問題――自分自身に固定された衛生というものの価値観を変えてみる事だった。ヒヴァではホテルの風呂はお湯が出なかった。エア・コンも故障が直らなかった。ホテルの人は修復しようとしてくれたが、だめだった。機械は故障する、仕方がない、とその顔は語っていた。水洗トイレも、トイレットペーパーを流せなかった。例外は有ったが、流すなという貼紙の指示に我々は従った。各地に有った有料トイレは有穴で、大概(おおむね)清潔ではあったが、便臭がひどかった。だが人は、他のすべての生物と同じ、食べて出す生き物である。臭い物に蓋をしても、それは隠せない。
ウルゲンチからヒヴァへ、そしてブハラからシャフリサーブスへ行く街道を走る車は、大方が型の古いもので、後部など塗装が剥げて錆び落ち、言葉の意味通り、尻切トンボになっているものも多かった。車体はもちろん、土ぼこりにまみれたままだ。それでも車は走る。車に、人や荷を載せて走る以上の価値は不要だ。衛生に関していうと、何事も無くて幸運だった、とも言える。不衛生が原因で大事(だいじ)に到る人々が世界にはいる。だがここで重要な事は、ひとたび東京、あるいは日本を出てしまえば、別の価値観が待っている、ということだ。自分の考える事、そして強いられるものは絶対ではない。価値観を相対化できれば、心は軽くなれる。
そしてこの頃から、旅を楽しむ余裕が出てきた。翌日、ホテルでの朝食の時、ブドウを食べてみた。一体、ウズベキスタンは果物と木の実が豊富である。ホテルでよく出たのはそのうちの、何種類かのリンゴ、そしてブドウである。ブドウは紫と緑の2種がある。いずれも粒は揃ってはいず、大きくて直径1.5cm、小さいものは5mm程、それが一房に実っており、一房は10cm~14、15cmくらいである。形に不自然さが無く、太陽と水の恵みで育った事がよく解る。味はすばらしく美味であった。宝石のように扱われる日本のブドウを見、味わうと、ウズベキスタンの人は、おいしいが、これは何という果物か、と問うに違いない。
3. シャフリサーブス
ブハラから次の目的地シャフリサーブス、ティムールの生誕地へ、車で4時間。この4時間は、運転するUさんも苦労、載っている我々も苦行、と言わざるを得ない時間であった。長距離移動は平気か、と最初にTさんに尋ねられた意味が、走るにつれて解ってくる。道路のデコボコが酷い。車のサスペンションが甘く、上下左右に激しく揺す振られる。Sはしかし車の乗り心地よりも、対向車の荒い運転に身の危険を感じた、という。センターラインの無い道を、対向車はものすごいスピードで走って来る。車線を食(は)み出しても憚(はばか)らない。スピードを出しているのはこちら側の車線も同じだ。この中を横切る勇悍(ゆうかん)な車もあった。信号が無いのだ。脇道からロバに曳(ひ)かせた荷車が出てきた事もあった。そのたびに、車の列が乱れ、我々の車は揺す振られる。だがその替わり、外の景色はすばらしかった。
左右、見渡す限りの礫(れき)砂漠で、街道両側に跡切れ跡切れに、背の低いサクサウールという灌木(かんぼく)の並木が現われる。砂礫地(されきち)には点々とタマリスクが生え、ヒースのような紅色の花を付けている。日本ではギョリュウ(御柳)という名で図鑑に載せられ、落葉小高木、樹高5~8m、とあるが、ここではやっと30cm程で、草のように見える。他には、鹿を護るフェンスと、ガス田(でん)からのパイプが延々と続くくらいで、何も無い。礫砂漠のこの美しさが、私に悪状況での4時間を堪えさせたといえよう。
だが車の震動は続き、吐き気を覚え始めて、車には居住性も必要だ、と無節操に価値感を変えかけた頃、シャフリサーブス(緑の町)に着いた。
緑の町は土ぼこりと重油の匂いに満ちていた。来年、アムール(支配者、大守、将軍などと訳される)=ティムールを記念する大祭がある。それに向けて街中が大改造されている最中であった。Sは事前にその情報を得ており、マスクを用意していて、私にも一つくれた。
我々はうなりを上げるパワーショベルやトラックの脇を抜け、ティムールの「白い宮殿」アク=サライを見学、彼の孫のウルグベクの建てた「瞑想の家」ドルッティロヴァット建築群、ティムールが息子のために建造した廟のある、ドルッサオダット(大いなる力の座)建築群を巡った。後者の建築群の中にあるハズラティ=イマーム(指揮者)=モスクは、現在も活動中らしく、建物の入口近くにいた黒衣の、僧かと思われる老人に、近よらないよう厳しく注意された。モスクの周りにはニレやクワなどの樹木が植えられ、どれも樹高が高い。静謐(せいひつ)さに満ちた空間は、私を敬虔(けいけん)な気持ちにさせた。ドルッサオダット建築群は、ティムールの宮殿から伸びる大通りを800m程の処にある、大通りに面した「瞑想の家」の前を通って、東に折れ、さらに細いくねった道を300m余り奥へ入った場所にある。そしてこの奥まった場所にも、改造の工事は及んでいた。
道の片側に並ぶ住居は取り壊し中で、瓦礫と生ゴミ、汚物の山となっていた。北京オリンピックで中国政府は北京の古い住宅を壊して撤去したが、それと同じことが、シャフリーブスでも行われていた。ドルッサオダット建築群からの帰りがけ、この道の途中で、我々は輝く瞳を持った少年に「コンニチワ」と声を掛けられたのだった。シャフリーブスでの壊されていく住居の光景と、この少年の瞳は、旅の中で一番印象に残った。
先にも触れたが、ティムールは、チンギス=ハーンの息子チャガタイを祖とする、チャガタイ=ハン国で軍人として頭角を顕(あらわ)し、1370年前後にアムールとなった。その「偉業」の最初は、チャガタイの甥フレグのイル=ハン国の征服であった。そして彼は1405年の死までの短い期間に、パキスタンからイラン、イラク、シリアまでを含む地域を征して、ティムール帝国と称される国を造った。帝国は彼の死後分裂状態となっていくが、イル=ハン国の先進的な文化は保護され、それを受容してティムール帝国の文化は成熟、トルコ=イスラーム文化として実を結ぶことになる。我々が土ぼこりの中で見た、ティムールの巨大な宮殿は、Tさんの説明では、遠征したインドの建築文化に触発されて、その大きさを越えようとして建造された。1398年のそのティムールの侵入を受けたのは、トルコ系のトゥグルク朝と思われる。デリー=スルタン朝と総称される王朝の一つである。16世紀の前半に、この王朝に替ってムガル帝国が建てられる。帝国を興こしたのは、詩人としても高く評価されるバーブルである。彼はそしてティムールの子孫であった。ティムールはウズベキスタンの英雄である。モンゴルにとってチンギス=ハーンがそうであるように。
さて、ティムールが彼の帝国の首都としたサマルカンド――オアシスの道(いわゆるシルクロード)と、カスピ海の北へ延びる草原の道とを行き来する人々の、交叉点として栄えたその都が、我々の最後の目的地である。そこには、先のトルコ=イスラーム文化を保護した一人であり、自らもその文化に親しんだ、心引かれる人物ウルグベクが待っている。
4. サマルカンド
サマルカンドへは、車で1時間の行程である。シャフリサーブスの中心地を離れるにつれ、彼方に長い山脈が見えてくる。パミール高原、あるいは天山山脈から続く山々である。サマルカンドは盆地なので、この山脈を越えて行く。最高地点で1600mの山の、峠を。
道の両脇は、大きいもので2、3mはあろうかと思われる岩が重なっている。上から道路へ今すぐにも落ちて来るのでは、と思われる程だが、もちろん道にガードレールが無いのと同様、落下を防ぐ措置は一切とられていない。岩と土だけの山には、所々に放牧された羊がいる。車の窓から見える範囲には、背の低いポプラやニレらしき木が点々と生えている。サクラのような木もあった。姫リンゴの果実にそっくりの、しかし色はオレンジのそれを、全身にびっしり付けた、野性のリンゴの木はよく目立った。アーモンドも、野生が生えているという。美しくて、見飽きることがない。途中、車を停めて、Tさんが焼肉レストラン(2軒ほど見かけた)で、塊の羊の肉を購入、その間に我々は、Uさんにブドウをご馳走になった。Uさんはブドウをレストランの前に引かれた水で洗って、我々に与えた。山のどこかに、水が湧く場所があるらしい。やがて木々の背丈がだんだんと高くなっていって、町が近いことを知らせた。
現在のサマルカンドは都会であり、いわゆるサマルカンドブルーのモスクや廟は、街の建物の間に点在している。
夕方着いた時には、まだシャフリサーブスの暑さの余韻の中にあったが、翌日は冬の寒さとなった。乾燥した寒さは身にしみる。風も強かった。チンギス=ハーンが「徹底的に破壊」した証拠として、現在も開発禁止になっているというアフラシャブの丘、かつてここには城壁に囲まれた町が在った。長い歴史の各時代が何層にも重なっている。掘れば今も陶器の片(かけ)らくらいは出るかもしれない、とTさんにそそのかされて、我々は丘を歩いた。しかし、遺物を探すことより、この曇天がどうにか晴天に変わってくれないものか、と気もそぞろだった。丘は延々と続いており、その広大さに「東京ドーム何杯分?」と言ってTさんを笑わせる余裕が、暖房された車の中では有ったのだが。チンギス=ハーンがこの丘を陥落させ得たのは、その水源を断ったからだという。「軍師は誰?」と、Sが笑った。
サマルカンドではやはり一見すべきだろう、と思っていた、シャーヒズィンダ廟群は、10を越える墓廟が、アフラシャブの丘の麓に、傾斜した地形なりに建ち並んでいる。最古の廟は11世紀の建築で、ここには預言者(ムハンマド。Tさんは最後までムハンマドの名を口にしなかった)の従兄の墓石がある。この、預言者の従兄が葬られている廟の存在が、他の廟が続々と建築される誘因となった。いずれの廟も、ブルータイルやブルーの模様タイル、青色の手描き模様などで、意匠を凝らして装飾されている。日射しも出て来て輝くばかりだが、しかし、期待に反してその美しさは、心を動かされるものにはならなかった。一体、タシケントでタカルダシュ=メドレセを見て以来、興味の中心はメドレセ(神学校)に移っていた。メドレセは構造上、中央の講堂の左右に、二階建ての建物、1階が教室、2階が寮、が延び、それらが中庭を取り囲むスタイルを採っている。ヒヴァのホテルはこのメドレセの建築様式を踏まえて、教室と寮を思わせる二階建て客室棟と、中庭で構成されており、中庭には、ニチニチソウやハゲイトウなどが見事に植栽されていた。
イチャン=カラ内のカズィ=カラーン=メドレセは装飾は簡素で、小ぢんまりとした造りだった。中庭が美しい庭園となっていたタシケントのメドレセと違い、現在は使用されておらず、庭は石で畳(たた)まれていた。しかしその小さなメドレセのたたずまいは、不思議に人の暖かみに満ちていた。
ところで、先のシャーヒズィンダ廟群の石段にも言い伝えがあった。門を入って最初の廟に登る石段の、往路復路にその段数を数え、それが一致すると天国に行ける、とTさんに教えられ、日本の神社にある、往復の段数がどうしても合わない口承を思い出しながら、試してみた。驚くべし、数は一致。えっ、という思いを抱きつつ車に戻った。異教徒にも恵みがあるだろうか。
廟群の南東には、アフラシャブの丘に替わって町の中心となった、レギスタン広場がある。日射しは安定し、広場の三つのメドレセの、襞(ひだ)のある青いドームを燦(きらめ)かせた。三つのメドレセは中央の広場を囲んで、ちょうど凸形に並んでおり、左(西側)に位置するウルグベクの建てたメドレセが最古で、15世紀初期の建築、あとの二つは17世紀に建てられた。ウルグベクのメドレセの、左右、2基あるミナレット(塔)の、右側のそれは傾(かし)いでいる。建物自体も傾(かたむ)いている、とTさんは我々の注目を促した。中央奥のティラカリ=メドレセもかつては傾(かし)いでいた。これは、砂地(レギスタン)が建物の重さに耐えられなかったためだ、と教えられる。Tさんは、これらのメドレセはすべてソヴィエト連邦下時代から修復が始まった、と言って、我々をメドレセ内に案内した。そこには、古い写真が展示されていた。そしてその写真には、あたかも広島の原爆ドームのように、崩れ落ちているメドレセが写っていた。我々はその有様に衝撃を受けた。三つのメドレセはいずれも、人の手を経て蘇(よみがえ)ったものだった。その「成果」を、我々は眼前にして来た。だがその修復の営みを、何と表現すべきなのか。それは私の思考を越えて、言葉として結ぶことができなかった。
サマルカンドにはウルグベクが関わった建物がたくさんある。レギスタン広場のメドレセや、先の廟群の入口の門もそうであったが、著名なのはグリ=アミール廟(支配者の墓)だろう。この廟は、ティムールの戦死した孫の建てたメドレセが基(もと)となっている。その地にティムールは孫を悼(いた)んで廟を建て、自身の遺体もここに葬られることになった。ウルグベクは祖父ティムールのために、あたかも家康の日光廟を、大建造物に造り替えた家光のように、廟を改造、墓室を黄金で荘厳した。ウルグベク自身も、祖父の足許に眠っている。ティムールの墓石は黒曜石で造られており、サマルカンドの交貿の一端を思わせる。ウルグベクのそれは、一回り以上小さい、つつましやかな大理石造りであった。
廟内で目を引いたのは、聖人の墓である。
ティムール一族の数基の墓石とは一画して設(しつら)えられた段の上に、それはあった。なぜ聖人の墓と判るのか、という私の問いに、Tさんは、墓の頭部側に立てられた背の高い木の棒に、ヤクの尻尾の毛が吊り下げられているからだ、と答えた。古びて黒ずんだ棒は直径20cmくらいで、一体何の木か、と我々は詮索したが、ニセアカシアか、ポプラか、と、聖人をと弔う作法が解らない我々の意見は分かれた。私の注目は、聖人の墓がアミールの廟内に残されていることだった。先住の神の祠(ほこら)を築城時に城内に残す者もいるが、城外へ出す武人も多くいる。この聖人の墓は、ティムールの孫のメドレセ時代から有ったのか。廟と成した時、誰も外へ移動させなかったのか、ムスリムの、神への帰依の深さが、聖人を虔(つつし)み敬(うやま)わせたのか。
ウルグベクの本領は、しかし、廟にではなくメドレセにあると思われる。ウルグベクは多くのメドレセを創建した。そして創建した主旨こそが、真の本領だった。彼は自身も科学者であり、学問と文化に理解が深かった。知識は彼の重んずるところであり、それゆえメドレセを造ってムスリムの子弟の教育に供した。しかもその教育は、男にだけではなく、女にも均(ひと)しく施されるべきだ、と考えたことにある。その彼はそして戦いより平和を好んだ、という。「生まれるのが早すぎた」とTさんは言ったが、四代目のこの後継者は、あたかも太田道灌のように、その先進性を嫌われて謀殺された。ウルグベクの生没は1394―1449年、享年55。一休宗純が同年の生まれである。
科学者としてのウルグベクの業績のシンボルは、天文台と、その内にある巨大な六分儀である。この六分儀を使って、彼と彼の招集した各国の学者の作った天文表の正確さは、17世紀にはヨーロッパに知られた。地下に6分の1、11mのみが遺されている、六分儀を見学したのは、アフラシャブの丘を降りた後で、寒さは一層強くなっていた。天文台の中にはヨーロッパのツアー客が何組も訪れていて大混雑。「ちょっとゴメンなさいね」という感じで、六分儀を護(まも)る柵の前へ進んだのだった。地下からは、ほんのりとした温もりが伝わってきた。Tさんの子供の頃は、今ほど厳重な柵は無く、六分儀に降りたことがある、と言って、その表面に刻まれた、観測のための印を見てみたかった私を、大いにうらやましがらせた。
これまでの行程で得たものの重みか、ウルグベクの成した業績に威圧されてか、グリ=アミール廟でTさんに撮ってもらった写真の中の、私の顔は疲れていた。肉体的な疲れは、夕食にレストランで食べたシャシリク(ケバブの玉ネギ添え)と、Tさんに誘われて飲んだビール(パルサーか)のおいしさが、心地よく解(ほぐ)してくれた。だが精神的な疲労(偉大なものも人を労れさせる)は、この旅行の果実が熟して心の中に消化されるまで、続くにちがいない。
我々のツアーは、いわゆる「シルクロード」の旅、と謳(うた)われていた旅行である。奈良の正倉院に納められている御物(ぎょぶつ)には「シルクロード」を経て到来したものがある、と教えられてから、そして日本の火祭りは少なからずゾロアスター教の影響を受けていると知って以来、この「絹の道」は特別の道として私の記憶の底に残っていた。その記憶が「サマルカンド」の名で数十年ぶりに蘇(よみがえ)った。ブハラやサマルカンドは、「絹の道(オアシスの道)」と草原の道の交わる地である。ソグディアナの商人らによって西から東へ、その逆へと、文物が運ばれ、文化も交流した。だが道は、文物や文化を運ぶだけではない。それは「侵略者」をも運ぶ。しかし反面、「侵略者」もまた、人や文化を運ぶことを否定はできない。アレクサンドロスが、唐が、イスラーム王朝がそうであったように。そして彼らによってまた、新たな道がつくられる。我々は歴史をどう活かせばよいのか――。
サマルカンドの明け方、ホテルの窓の外、昇って来る朝日のもたらす薄赤い曙光(しょこう)の中に、西へ沈んでいく満月を見つけた。思いを交錯させながら、満月に向ってシャッターを切った。
5. 旅のおわり
ツアー最終日を迎え、我々はサマルカンドから長距離列車で3時間半、列車の中では韓流風のウズベキスタンのドラマ(言葉がまったく解らないにもかかわらず、筋は充分に追える優れもの)を楽しみつつ、首都タシケントに戻った。
初日に、ナショナルホリデーということで見残した、タシケント歴史博物館を訪れ、日本人墓地に参拝した。第二次大戦の終戦時に、ソヴィエト政府によってタシケントに連行され、土木工事や建設作業の強制労働に従事させられた人々の墓である。墓石に肖像を彫(きざ)んだロシア人の墓や、丸いドーム型の土まんじゅうのムスリムの墓の奥の一郭に、人々は整然と埋葬されていた。
7日間に及ぶ旅、その一日は優に一週間かそれ以上に匹敵した感のある、我々の旅は、完了した。心残りはただ一つ、さらさらした細粒状の、ウズベキスタン唐辛子を買えなかった事である。辛みより風味の勝つその唐辛子パウダーは、麦と米の混じったミルク粥に懸けると、実に美味なのであった。
◆参考文献◆
地球の歩き方編集室『地球の歩き方 中央アジア サマルカンドとシルクロードの国々』
(ダイヤモンド・ビッグ社、1913年)
![旅行記[旅のクチコミ情報]](/assets/css/gone/head.gif)